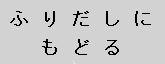宮沢賢治の小品『猫』について
(宮沢賢治は猫嫌い?)
それは20年も前に読んだ、賢治の雑稿のような十数行の、まったく謎の文章。今でも頭にこびりついている一行。
(私は猫は大嫌ひです。猫のからだの中を考へると吐き出しそうになります。)
これはあんまり不思議だったので、長く心に残り、しばしば思い出しては首を傾げていました。
河合隼雄先生もこの小品に着目され、
「賢治は実は猫嫌いで、しかし作品に多く登場させるのは、作家として猫の心的象徴を自由に使ったのですよ。別に、好き嫌いで書いてる訳じゃ、ないんですよ。」
と言う風な見解を提示しておられます。(『猫だましい』 新潮文庫 p113 )
この作品は、いま調べてみると、そのまんま『猫』と言う題名で、いかにも雑稿、覚書のようですが、カッコでくるんだ文章と本文(?)が、戯曲のように交互にあらわれ、形式的にも整った、精錬された詩のようにも見えます。私の頭の中でいま、脈絡なく鳴っているのは、『ドン・ジョパンニ』の最後の、亡霊との対話です。悪漢ドン・ジョパンニが、いよいよ地獄に、引き込まれて行く所です。
こりゃちょっと、全文掲載せんといかんようですね。サービスでカッコ内は紫色。それぞれに読んで、おごやいっ。( 「おごやい」とは、「ください」の東北風の言い方。ますむら先生がたまに使われる。しかし、説明なしでもだいたい通じるのは、不思議ですね。 )
『猫』 宮沢賢治 作 (と言うか、筆? (『ザ・賢治』 -宮沢賢治全一冊 - 第三書館 p289より )
(四月の夜、とし老った猫が)
友達のうちのあまり明るくない電燈の向ふにその年老った猫がしづかに顔を出した。
(アンデルセンの猫を知ってゐますか。
暗闇で毛を逆立ててパチパチ火花を出すアンデルセンの猫を)
実になめらかによるの気圏の底を猫が滑ってやって来る。
(私は猫は大嫌ひです。猫のからだの中を考へると吐き出しさうになります。)
猫は停ってすわって前あしでからだをこする。見てゐるとつめたいそして底知れない変なものが猫の毛皮を網(あみ)になって覆ひ、猫はその網糸を延ばして毛皮一面に張ってゐるのだ。
(毛皮といふものは厭なもんだ。毛皮を考へると私は変に苦笑ひしたくなる。陰電気のためかも知れない)
猫は立ちあがりからだをうんと延ばしかすかにかすかにミウと鳴きするりと暗の中へ流れて行った。
(どう考へても私は猫は厭ですよ)
いかがですか? これは立派に作品として練られた文章 ……… だって、
◯ 猫は四月の夜と言う、おどろしい時に、闇から現われて闇に消えて行く。
◯ 滑ってやって来て、流れて去って行く。
◯ 一二行目は「兼ね合い」。だんだん「離れる・後ろに回る」と言う、演劇的、音楽的な「技巧」を使っている。
つまり、体裁が整っているのです。
「なめらかによるの気圏の底を」とか、「毛皮を網(あみ)になって覆ひ」とか、表現やイメージにも重みがある ………
こりゃ単なる雑稿やメモではない。
読み手を意識した、作品として練られたもの ………
さて、内容ですが、
つめたいそして底知れない変なものが猫の毛皮を網(あみ)になって覆ひ、猫はその網糸を延ばして毛皮一面に張ってゐるのだ。
このイメージが、この小品の眼目ですよね。いったい、何の事でしょう?
猫がぺらぺら顔や頭をなでさすり、網のようなバリア、陰電気の電磁スクリーンを張っているのです。
まったく、解らない。単なる断片的なイメージ、妄想かも知れません。
それでこの部分は私の記憶にもなかったし、河合先生も引用しておられません。しかし一晩寝て起きたら、思い当たる事がありました。
体中にびっしりと書かれた経文は、まったく網の目のように見える。
これは、同じイメージを表現したものではないか?
この網がなければ、闇の中に身体が溶けてしまうからではないか?
芳一は、それで外から入ってくる悪霊から身を守ろうとした。ところが耳にだけ経文を書き忘れ、亡霊から耳をむしり取られてしまう。………
意識がどんなに完璧を期そうと、いや、するほどに、決定的な穴が開く。
そして意識には、それが解らない。目には光しか見えないからです。闇となると、お手上げです。
それでも意識的に必死の努力をしないと、すべてを、命までを奪われてしまう。
「芳一はこの危難を逃れて後に、ますます素晴らしい琵琶の名手と成りました。」
というのが、結末です。
立派に完成される人生でも、まさにその才能ゆえに、一度は闇との接触がある。
芳一は自分の人生と善に忠実だったから、気がついたら知らぬ間に、亡霊達のただ中で、請われるままに琵琶を演奏していたのです。その琵琶の技は、この世のものを越えていたので、あの世との境界を曖昧にして、亡霊たちを呼び出してしまったのです。
これに対しては意識的な努力で、必死に防がねば成りません。しかし闇から現われた『影』は、無残にも芳一の両耳を引きちぎってゆく ………
この「耳」と言うのは、琵琶を弾くのに大切な所である事を、強く指摘しておきます。( 実際に、ベートーベンやフジコ・ヘミングさんは、耳に痛手を負いました。……… フジコ・ヘミングさんは、バーンスタインの絶賛により実現した、人生で一番大事なコンサートの前日に風邪を引き、耳が聞こえなくなりました ……… )
大成功や、稀有な才能という強い光に照らされて、影はくっきりと姿を現す。( これも相補性、意識がバランスを取る性質によるものと思います。)
影との接触では、誰でも酷い犠牲を支払わねばならない ……… いや、生還できる者さえ、稀である ………
と言うのが私の解釈で、これはオーソドックスな解き方と思います。
( もちろん作家はこんな、屁理屈を垂れながら書いている訳ではありません。多少は参考にするでしょうが、そんな事をすれば、実に無残な事に成ってしまうでしょう。)
世にも稀な才能を持った者は、まさにそれ故に、あの世、無意識との境界を引き裂いて、『影』とまともに対面してしまう ………
とすると、『耳なし芳一』は、(原作の方の)『ゲド戦記 1』に似て来ますね。
しかし賢治の『猫』を読んで、「賢治は猫嫌い」と、そのまま額面通りに受け取るとは、まことに河合先生には珍しい事ですね。
「賢治の言う猫とは、実際の猫の事だろうか? これを闇、無意識の世界から現われた何かと考えてはどうだろう? それならば、その内容に呑みこめない、吐き出したく成るものが含まれていたとしても、当然ではなかろうか?」
と問い掛けるのは、普段なら河合先生の役割です。
だいたい最初に「 アンデルセンの猫を知ってゐますか 」と、かましているのです。
河合先生が何故ここを滑らかにスルーしてしまったか不思議ですが、とにかく「天才がたたらを踏む所には、何かある。」のです。
猫は昼間には夢の世界にいて、夜になると起き出して闇へと消えて行くもの。( 家猫は、この限りに非ず。)
猫は光と闇の間を自由に行き来するもの、人を闇へと魅了して誘う、異世界への案内人 ………(『 セロ弾きのゴーシュ 』でも、異世界への第一夜目に猫を持って来ています。)
人はアニマによって、魂(ゼーレ)へと導かれると言います。
猫はまったく、アニマそのものですね。
( ほど遠い猫も、おります。)
まあ、実際に猫を飼った事のある人なら、たいていは案外くだらない事、せいぜい紅マグロか酢ダコの事を考えているのは、よくご存知と思いますが。(笑)
( しかし本当に大切な事は、よく覚えているようです。私は何度か、人間として猫に負けた事があります。)
で、結局のところ、賢治は猫好きだったか猫嫌いだったか?
これは他の賢治作品の猫の使い方を見れば解ります。
賢治が作品に使う猫の役割は重く、『 どんぐりと山猫 』は、猫嫌いには思いつかないでしょう。
反対に、『 注文の多い料理店 』では、猫のマイナスイメージを効果的に、何らためらわず使い、これはべたべたの猫好きには書きづらいでしょう。
河合先生の言われる通り、猫の効果を縦横に駆使しております。
これらを考え合わせると、賢治は猫好き、猫嫌いと言うより、猫使いだった。
そして猫はいつも、賢治の傍にいた。
私はそう思います。
そもそも「 私は猫は大嫌ひです。」と言うのは、猫に対する発言ではありません。例えば『 猫の事務所 』の、
「 猫なんていうものは、賢いようでばかなものです。」
というセリフは、明らかに「 人間なんて 」と言っている訳でしょう?
この作品中の猫だけが、実際の猫を指してるとつい考えてしまうのは、あまりにも訳の解らない作品だからでしょう。これは河合隼雄さえ引っ掛ける、賢治の超絶技巧です。
漱石をはじめとして、作中に猫を登場させる作家は、たいてい実際に猫を飼った事があり、少なくとも相当に面白がって猫を見ていました。これは猫嫌いには難しい事です。
そして「好き」と言うのがいつも、それが自分自身の大切な何かであると言う表明ならば、つまり、もし賢治が猫好きだったのなら、かの作品は、次のように言い換える事も出来るのです。
次の文章の文学的な意味や価値は、あなたに
『 アニマ 』( 書き換え。大雑把に乱暴な事を言うと、アニマは自己自身。)
(四月の夜、とし老った自分自身が)
友達のうちのあまり明るくない電燈の向ふにその年老った自分自身がしづかに顔を出した。
(アンデルセンの自分自身を知ってゐますか。
暗闇で毛を逆立ててパチパチ火花を出すアンデルセンの自分自身を)
実になめらかによるの気圏の底を自分自身が滑ってやって来る。
(私は自分自身は大嫌ひです。自分自身のからだの中を考へると吐き出しさうになります。)
自分自身は停ってすわって前あしでからだをこする。見てゐるとつめたいそして底知れない変なものが自分自身の皮膚を網になって覆ひ、自分はその網糸を延ばして皮膚一面に張ってゐるのだ。
(皮膚といふものは厭なもんだ。皮膚を考へると私は変に苦笑ひしたくなる。陰電気のためかも知れない)
自分自身は立ちあがりからだをうんと延ばしかすかにかすかにミウと鳴きするりと暗の中へ流れて行った。
(どう考へても私は自分自身は厭ですよ)
この言い換え、正鵠を得てはいないが、方向は正しいと思います。
最も正しい言葉の選択は、おそらく ………
ちょっと考えてから、下をクリックして下さい。あなたはきっと、正解を知っていますよ!
何か、プラウザによっては、ダイアログボックスがうまく現れないので書いて置きますと、
答えはやはり『 猫 』です!